子猫の学び方 |
|
目が覚めると隣に愛する人が居なかった。 滅多にオレより先に起きる事は無く起きていてもじっとオレの顔を眺めているか、擦り寄ってきていた。 そんな可愛らしい仕草をする彼が今朝はいないのだ。 オレから離れるのを嫌う彼が。 もしかしたらそう思っていたのはオレだけだったか…。 色々と思考しながらも彼を探した。 「おはようございます、ご主人様。」 愛してやまない可愛らしいオレだけのネコ、もとい恋人は紅茶を用意していた。 しかも今、オレの耳がおかしくないのなら『ご主人様』と聞こえてきた。 ネコ耳ネコ尻尾には定番だとアメリカに居たとき学んだ、その通りに。 あの、恥ずかしがり屋で滅多に『好き』だとは言ってくれないユーリが。 「ご主人様…?」 小首を傾げて見上げる姿はいつもと変わらない。 違うのはオレの呼び名だけ。 「あぁ、おはようございます。」 何も言わないオレを不安に思ったのかきゅっと服の裾を握られて我に戻った。 漆黒の瞳が揺れている。 「紅茶淹れたんだ。飲も?」 うるるんと見上げてくるユーリを思わず抱き締めてしまう。 心の中で可愛いーー!!と叫びながら。 とりあえず擦り寄ってくる可愛らしい人を抱き上げてテーブルへと向かう。 ネコユーリ専用の椅子に座らせると珍しく抵抗された。 「ユーリ…?」 「俺が淹れるの。ご主人様は座ってて。」 椅子に無理やり座らせられて待たされる。 危なっかしい足取りでお揃いのカップを持ってくると、これまた危なっかしい手つきで紅茶を淹れる。 紅茶がたっぷり入ったティーポットはやはり重いのか手が震えていた。 手助けをしようとすれば、きっと睨まれて座りなおす。 それのやり取りを何度かしたところで紅茶がカップに収まった。 当然というか、そのカップの周りは零れた紅茶で濡れていた。 そっと拭いてやると目尻に今にも零れそうなほど涙を溜め、唇がわなわなと震えている。 いつもと勝手が違うユーリに思わず頭を抱えたくなった。 とりあえずへたりと垂れた耳を撫でながら紅茶を飲む。 丁度良いほろ苦さに頬を緩めた。 「どう…?」 ものすごく心配そうな顔で見上げてくるユーリの頭を撫でる。 「とっても美味しいですよ。オレより淹れるの上手いかもしれません。」 パタリと揺れる尻尾が腕を掠める。 じっとオレを見つめた後、紅茶に手を付け出した。 口にした途端、がたりと音を立てて立ち上がった。 紅茶が残っていたティーポットを持ったと思うと、シンクに流す。 「ユーリ!?」 突拍子もない行動に驚いているとオレのカップを持ってシンクへ向かう。 慌てて止めにかかるが一歩遅く、目の前で排水溝へと吸い込まれていった。 よく見れば、ユーリの目からはポロポロと涙が零れている。 「どうしてこんな事したんですか?」 落ち着かせるように頭を撫でるときゅっと唇を噛む。 血が滲んでしまういそうなほど噛むので、キスをして口を開けさせる。 少しでも唇を離すと噛もうとしたので、無理やり舌を捻じ込ませて閉じれないようにした。 逃げ惑う舌を捕まえて絡め、きつく吸うとカクンと膝が砕ける。 ユーリが床に膝を着く前に、裏膝に手を回してお姫様抱っこをした。 軽くキスをしてそのままベッドルームへと連れて行く。 体に力が入らないのか、ユーリは抵抗もせず弱々しく服を握っていた。 「ユーリ。」 ベッドに降ろすと、くすんと鼻を鳴らしながらポロポロ涙を流す。 最近、鳴かせてばかりだなと後悔しつつも、あの行動の理由が知りたかった。 オレのために淹れてくれた紅茶。ご主人様と呼んだ理由。 嬉しかったのに。 「美味しくなかったから…。」 シーツで顔を拭きながらポツリと答えられた。 それが紅茶を捨てた理由だと気付くまでそうかからず、そしてまた頭を悩ませた。 おいしくないはずなどなかった。とても美味しかったのだ。 ましてや、ユーリがオレのためだけに淹れてくれたのだ。どんな紅茶よりも美味しいに決まっている。 しかし、どんなに考えてもユーリの考えにはたどり着かなかった。 「とても美味しかったじゃないですか。オレは好きですよ。」 「美味しくない。苦かったもん。ご主人様の淹れてくれる紅茶の方が美味しかったもん。」 確かに、オレが淹れる紅茶よりは苦かった。 だが、それは紅茶の葉が違うからであって、決してユーリの淹れ方が悪いわけではない。 オレがいつもユーリに淹れるのは甘いフレーバーティー。 今日、ユーリが入れてくれたのはストレートのセイロン。 どちらもわざわざ地球から取り寄せたものだ。 少しでもユーリにリラックスしてもらえるようにと。 もしかして…。 「苦かったって、ユーリがいつも飲んでいるのよりもですか?」 オレの質問にきょとんとした顔をして見つめてくる。 「それ以外に何があるっていうんだよ!」 涙で潤んだ瞳で睨んで、まだもシーツに顔を埋める。 どうやらユーリは紅茶の知識がてんでないようだ。 ピスピスと鼻が鳴る音が可愛らしくて頬を緩めてしまう。 ユーリが見ていなくて良かったと思いながら、いつもの顔を作る。 「ユーリ。紅茶の葉が違ったんですよ。 オレが淹れているのはフレーバーティーという果物の匂いなどが付いた紅茶の葉で、 今朝ユーリが淹れてくれたのは、セイロンのストレート。元々甘くないヤツなんですよ。ほんのりとした苦味も特徴です。」 優しく耳の付け根を撫でてやりながら説明する。 取りあえず泣き止んだようで、シーツで顔を擦っていた。 あとで冷やしたタオルが必要かなと考えながらユーリを見守る。 「じゃぁ、オレいらなくない?捨てたりしない?」 目尻に命一杯涙を溜めながら見上げてくるユーリ。 全く話が読めずに返事に困ると、捨てられるんだと呟いてまたも泣き出した。 珍しくオロオロとしながらユーリを宥める。 「捨てないで。いい子にするから、頑張ってご主人様のお世話するから…捨てないで。」 必死にオレにしがみ付きながら懇願するユーリに征服欲を感じながらも何とか落ち着かせる。 とりあえず、何故そのように思っているのかを聞き出すのが先決だ。 「いらない子は捨てられちゃうって。」 毒女の本を指さして言う。 そういえば昨夜、寝る前に何やら真剣に本を読んでいるなと思ったら…。 読んだ子供がおねしょをしてしまうほど恐いというその本。 取りあえず読んでみる。 内容は屋敷で奉公する子供が捨てられてしまうという単純明快なものだった。 その子供は一度も雇い主をご主人様とは呼ばずに、なおかつ、悪戯をよくしていた。 今のユーリそのものだった。 それで今朝からおかしかったのだろう。 しかも、ご機嫌取りに淹れた紅茶はいつもとは違う味で、さらにパニックを引き起こした。 解かってみればなんともなく、そして不安にさせてしまっているんだなと後悔した。 「ユーリを捨てるわけありませんよ。どんなに嫌がったって離しませんから。」 後悔しても遅いですよと囁くとさっきまでが嘘のように微笑んで。 「絶対に離さないで。」 と、触れるだけのキスをして擦り寄ってくる。 キスの味はほろ苦く、そして少ししょっぱかった。 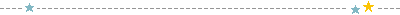 子猫シリーズ、久々の更新です;; トロくてすみません。 取りあえず今回のコンセプトは「ご主人様」です(笑) 前から言わせたかったんですよね!コレ! 今回叶えられて幸せです(笑) 砂吐きの予定だったんですが…吐けました? ……温いですよね;; もっとラブラブにする予定だったのですが…。 次こそは甘いのを目指します! 指で水を飲ますとか!(笑) by aya kisaragi | |


